下宿がへ(一)
坂の上の雲 > 正岡子規 > 友人子規 > 東京篇 > 下宿がへ(一)
「筆まかせ」の「下宿がへ」に子規は次のように書いている。
下宿がへ
書生の下宿替えの頻繁なるはいうまでもなきことにて、半年ぶりに朋友の処より来た手紙には四五枚の付箋をつけて数週間の後に来ることさえ屡々あるなり。余はさまでに下宿をかえることはきらえども(性懶惰にして動くことがきらい故)動くとなると遠方へ動くのが通例なり。故に余が出京已来寓居の地を数うるに区をかえることしばしばなり。明治十六年出京して日本橋区に住し、一箇月許りにて赤坂区に転じ、また二箇月余にて日本橋に帰り、一箇月を経て神田区に移る。翌十七年夏牛込に転じ、秋再び神田に来り、十八年夏帰省し、再び出京して麹町区にあること二三日、又もや神田の下宿(前のと同じ処)に至り、十九年夏麻布に行き、一箇月許りの後また神田に行き後同区内駿河台に転じ、二十年四月一ツ橋外中学寄宿舎に入り、二十一年夏向島須崎村(今は本所区になれり)に寓する三箇月、遂に本郷に移転し、本年十月また今の下谷区に来れり。その移転恰も野蛮人の水草を追うて転居するが如く、檐端《のきば》に立て廻り燈籠を見るに似たり。
右の文末に本年十月とあるは明治二十二年のことなれば、子規はその出京の十六年夏よりここに至る約六年間に下宿を替えること十五回の多きに及んでいるが、その移転の年月と下宿所在地の区名を挙げて町名、下宿名は一切これを省略し細説せざるために、その下宿が果して何町のどこにあって何と称する下宿でありしかを知る能はず、東京における子規の居蹟を探らんとする者にとってはこの点甚だ遺憾とさるるところなれば、予は我が記憶と資料とに依りて聊か解説を加え、その不備とせらるる町名、下宿名の判明せんことを期したいと思う。本稿は即ちこの目的を以て語りすすめらるるのである。
「明治十六年出京して日本橋に住し」と先ず記されているが、それは浜町二丁目十七番地の旧松山藩主久松伯爵邸のことである。然るに子規は着京後十日ばかり予の下宿に居て親戚めぐりなどに日を暮らしたれば、その間のこと予め語りし後浜町に及ぶとしよう。
子規は明治十六年六月十四日新橋駅に着いた。我国の汽車といっては当時東京横浜間に限り、且つ新橋駅が東京での発着駅であったから、この駅に降車せし次第である。「筆まかせ」の「東京へ初旅」に子規は当時の第一印象を次の如く語っている。
去年六月十四日、余ははじめて東京新橋停車場につきぬ。人力にて日本橋区浜町久松邸まで行くに銀座の裏を通りしかば、東京都はこんなにきたなき処かと思えり。やしきにつきて後、川向いの梅室という旅宿に至り柳原はいるやと問えば、本郷弓町一丁目一番地鈴木方へおこしになりしという。余は本郷はどこやら知らねど、いい加減にいて見んと真直に行かんとすれば、宿の女笑いながらそちらにあらずというにより、その教えくれし方へ一文字に進みたり。時にまだ朝の九時前なりき。それより川にそうて行けば小伝馬町通りに出ず。ここに鉄道馬車の鉄軌しきありけるに余は何とも分からず、これをまたいでもよき者やらどうやら分からねば躊躇しいる内、傍らを見ればある人の横ぎりいければこわごわとこれを横切りたり。その後はどこ通りしか覚えねど大方和泉橋を渡り(眼鏡かもしれず)湯島近辺をぶらつき、巡査に道を問うすべをしらねば店にて道を問いながらようよう弓町まで来たり、一番地というて尋ねし提灯屋ありければ、ここに鈴木というて尋ねしに、この奥へまわれ、小さき家なりという。奥へまわるにどの家やら分からず、鈴木という名札を出したる処なし。遂にそこにある一軒の家に入りて問うて見んと「お頼み」と一声二声呼べば「誰ぞい」といいつつ出で来たりしは思いもよらぬ三並氏なれば、互いに顔を見合してこれはこれはというばかりなり。余ははじめこの家より出てくる人は知らぬ顔なり。もし知りたる顔ならば柳原ならんと思いしに、事不意に出でたり。三並氏も余の出京の事は露知らねば驚きて「まず上がれ」という。上がりて後柳原はと問えば今外出せりという。その時は最早十二時近かりしならん。色々の話の中に柳原も帰り来り、ここではじめて東京の菓子パンを食いたり。
右文中にある三並氏は子規の再従兄にしてまた五友の一人なる良氏のことである。氏は子規に先立つ一年明治十五年の夏出京し、予は一ヶ月前出京したのであった。この鈴木というは小石川の砲兵工廠の上なる壱岐坂の中ほどに在りし極めて小さな下宿屋にて、主人は何歳であったか忘れしが、六十歳ばかりの婆さんが一人で我々の世話をしていた。そこへ子規は出しぬけに尋ねて来て、数日間は我々と共に市内見物に出歩いたり親族訪問などをして悠々と過ごしていた。壱岐坂はその後改修されて当時とは大いにその趣を異にしているから、鈴木の址を今日示すことは出来難い。
子規は加藤の叔父の声がかりで出京が出来たのだから、何は措いても第一に加藤を訪わねばならぬと言って、着京の翌十五日に三並氏を道案内として出かけて行った。加藤拓川は当時病気療養のため向島の木母寺畔の東屋という料亭に下宿しいたもので子規等を迎えるや他の来客を避くるために近所の百姓家の一室に伴いてそこで会ったということである。拓川に将来の目的はと問われて政治家と子規が答えしというのはこの時のことである。拓川遺稿の日記を見るに、「十五日(六月)姪正岡常規自松山至与三並同来三並晩帰常規留宿」とあり、また「十六日常規去」と記されている。三並氏はその日の夕刻加藤氏の下宿を辞去し、子規は一泊して翌十六日に帰ったというのである。三並氏を帰しておいて、その晩子規は身上につきしみじみ懇談せしものと察せらるるのである。
久松家の家扶で拓川の友人である伊藤某と云うが「向島に拓川を訪いて四方山話《よもやまばなし》の際、後より来訪せし子規を見るや昨日初めて松山より出京せし正岡の子というのはこの少年かな、この子ならば先刻言問団子の店に悠然と座り込んで団子を喰いつつ徐《おもむろ》に隅田川の風光を打眺め、詩作でもするか何か考え込んでいたが、ホット出の田舎少年で東京の土を踏むや踏まずに早くも団子店に這入るなど肝が据わっている、将来頼もしいところのある少年だなと拓川に向かって嘆賞した」というようなことが何かに書かれていたのを見たと覚えているが、子規が初めて拓川を向島に訪いしは前にも語りし如く三並氏と同行せしもので、単独行ではなかったから伊藤某の言と合致し難い点がある。この月の十九日に子規は単独で拓川を再び往訪しているから、あるいはこの時の事かとも思わるるが、それでは「昨日初めて松山から出京せし正岡の子云々」が喰い合わない。この話はどうも合点が行きかぬるが、何は兎も角として子規にそれ位の度胸のあったことは勿論で、別に取り立てていうほどのことでもないと予は思う。十九日の再訪は拓川の日記に「十九日常規来訪」とあるに出るものである。
ここで本問題に入ることとする。日本橋区蠣殻町を東に突きつめたつめたところに蠣濱橋というがある。その橋を渡ったところに黒い大門が立ちふさがり、門の左右は例の大名屋敷におきまりの格子付きの高窓のある長屋が長くつづいている。前にも言ったこれが旧松山藩主久松伯爵の屋敷なのである。当時はここが久松家の本邸で、麻布に別邸があったが、後年芝公園の上に本邸を新築し濱町の方は処分となって他人に譲り渡され、自然取払われて解消してしまった。
長屋は壁一重で約十戸位に区切られ、家令をはじめ用人達の住宅となっていたが、大門から北へ数えて二番目か三番目の一戸が所謂書生小屋であった。誰が言い始めしものか、マサカ久松家がこんな名称を附する筈はないが、用人までが書生小屋と呼んでいた。旧藩地から出京する金無し書生輩が御願いすると、無償でここに置いて貰える事になっていたから、書生小屋の称呼が起こったものであろう。希望者の多い時は数名合宿であるが、時には一人も居ないで空き家になっていることもある。戸主といったような責任者がないのだから、掃除などは勿論完全に行われず、畳も破れ古び、壁も天井もくすぶり汚れて、見るから陰鬱なる六畳二間ほどの部屋であった。余も一時ここに厄介になって自炊したる体験をもつものである。
子規の這入った際には先来の合宿者が二三人あって、その者に少なからず虐められたらしい。かかる陋屋《ろうおく》に肉体的の苦痛を忍ぶのみならず、精神的にもまた不快を感じさせられては子規たるもの必ず遣る瀬がなかったであろう。「筆まかせ」の「自炊」と題する文中に子規は次の如く当時のありさまを語っている。
・・・・・・そもこの書生小屋というは邸内長屋のつづきなれば、南北は同じ長屋にて壁一重が隔てなり。入口は東にありて西は格子をうちたる三尺許りの高窓あるのみ。間口二間許り奥行四間許り、きたなき部屋二間と台所様の流しもと一坪程あり。家は幾年掃除せずやと衛生係が苦情をいいそうな、ふすぼりたる、昼も薄暗きところ、畳は焼け跡もあり、水、醤油などに煮しめられたるあとも見ゆ。ただ見てさえいぶせき処へはいりこみたる時は、牢屋へ行きしもこれほどにはあらじと思われたれどもせんすべもなし。同居人は二三人ありて同じ国の者なれども我よりは年もたけ、且ついやみ多き不淡泊なる性根のきたなき者のみ。かつ一面識あるかなきかの人なれば話もせず、また話すことも好まず。されど初めてここに行きし時は新囚人が旧囚に対する如く、已来は万事の指揮を受けねばならぬ人故「今日から参りました、お頼み申します」と挨拶し、多少の荷物を納戸などに入れて、先ずそれもすみたれば火鉢の前に坐りたり。この箱火鉢は半ば崩れ半ば焦げ、灰はかたまって塵をあげず、マッチのなきがらは墓碑の如く林立す。土瓶は底の方半分已上真黒にこげて下に火も灰もなき所を見たれば、炭はなくて薪をたきしものと思わる。いぶせきこといわん方なけどいう人なし・・・・
次には「一箇月許りにて赤坂区に転じ」と記されているが、これは同区丹後町九十九番地の須田学舎に寄宿せしをいったものである。赤坂見附より青山に向かう途中右側に豊川稲荷の社がある。その社前を左に入って少し行けば須田学舎址に出られるそうだが、予は曾て同地に立寄りしことがないので委しい話は出来ない。子規が須田学舎に入舎せし動機に就いては、藤野漸氏の後妻で古白の継母であった磯子刀自が次の如く碧梧桐氏に語ったことがある。要するに古白の監督お守役として暫く入舎することになったものである。
・・・・・・この中六番町にいる時分、主人が琉球へ出張することになってしばらく留守になることになった。その間、長男の潔-古白-を何処か塾へでも入れたいというので、加藤の叔父から赤坂丹後町の須田という漢学塾を世話して下さった。潔のお守役、まア監督というような意味で、升さんも同塾に入ることになりました。
須田学舎は漢学塾であったように磯子刀自は言っているが、漢学の外に英数学も教えられていた由、当時子規が語っていたように予は記憶している。斯くて規白両人は同学舎に在ること二ヶ月ばかりにして共に学舎を引き払った。それは九月二十二日であったと想われる。同日付にて竹村鍛氏に宛てし子規の書簡に「小生今日より日本橋区濱町二丁目十七番地久松邸へ移転したり」とあり、須田塾を引き払って再び久松屋敷の書生小屋に復帰した時の報知であろう。
須田塾に在舎中の状況に就いては子規の評論「藤野古白」に次のようなことが見えている。古白は当時十二歳の少年であったが、他人と調和が出来ず、誰を見ても敵のように思ってすぐ喧嘩を始める。唯口の争いばかりでなく腕力に訴える、手に刃物でもあれば必ずこれを以て敵に迫ろうとする。要するに敵の前に自己を守らんと計るのである。一種の恐怖心からである。斯かる僻心は何時から発生せしか、その原因は容易に窺知するを得ないが、古白は七歳にして実母・・・子規母堂の妹十重・・・を喪い、誠に気の毒な生い立ちであったと云うようなことを、子規はある時予に告げたことがある。
・・・・・・ほどなく古白は東京に移りぬ。明治十六年余が上京して赤坂に至りし時、塾舎を同じうせり。この時古白は他の塾生と喧嘩すること絶えず。先生は屡々彼を譴責し且つ余に彼を戒めよと命ず。居る数月余は退塾して神田の藤野氏に寄寓す。古白また同人社に入る。その同人社に在るやナイフをもて同学生を傷つけたりとて塾の監督より暫時帰宅を命ぜられ、余は同人社まで彼を連れに行きたることあり。
次はまた「二箇月余にて日本橋に帰り、一箇月を経て神田区に移る」と記されている。日本橋に帰りは前にいった書生小屋に帰ったことで、此処に再び自炊生活をしているうちに、一ヶ月を過ぎて神田区に転じたというのである。九月二十二日から一ヶ月といえば十月の末であったろう。神田区仲猿楽町十九番地藤野漸氏宅二階六畳の間に寄寓することになった。水道橋の方から云えば右側で、同町の中程であったと思う。東向きに門があり、門を入って西へ数歩すれば玄関に達し、少しの中庭もあった。玄関の奥に居間があり、その左が客間で、右が茶の間、茶の間の上が二階で即ち子規の室、茶の間も居間も各六畳で客室は八畳であったと記憶する。子規の室にモ一人寄食者があった。清水則遠といって子規の同郷生、年齢も略々同じ位のものであった。此処へ古白が同人社から戻されて来て後は、六畳に三人の机を並べて室内が相当混雑していた。
主人の漸氏は会計検査院かに奉職し年齢四十五六、夫人の磯子は二十四五歳、大分若い細君だなと思った。子規等はこの若夫人に世話になっていたのである。その若夫人も今では七十七歳の婆さんになっているが、頃日仲猿楽町時代を追憶し子規について次の如き思い出談を試みた。性来食い意地の強かりし彼、読書の盛んなりし彼の面目がこの談話中に躍動している。
・・・・・・相当の大食で、御飯もお八ツも人並みではすまなかった。宅では蚕豆《そらまめ》を煮ることがよくありました。古い蚕豆を水に冷やして柔らかくしたその皮をとるのを手伝ってもらいましたが、一升ほどの蚕豆は、大抵一度で無くなる位でした。
それで時々お腹をわるくする。宅の主人が、これからは毎食三杯、必ず生飯で食うように言いつけて、それを実行させましたが、ある時その茶碗が割れて、近所の勧工場へ買いに、私共と一緒に往った。升さんは、その中でも一番大きい茶碗をとって、これにします、というので、覚えず苦笑せずにはいられませんでした。
その時分、成島柳北という人であったように覚えますが「絵入自由新聞」というのを出して評判になっていた。その続き物が面白いというので、升さんから勧められてそれをとる事にした。毎朝奪い合って読む、私なぞはそれからどうなったか、それから升さんにその続き物の話をしてもらうといったあんばい。それがいつからか新聞がまだまだ来ないって、清水さんが待ちくたびれる、そんなことが度重なった。どうしたのかと思ったら、宅の二階から屋根づたいに堀のところまで出て、その下を通る新聞配達から、ソッと新聞を受け取っていた、それが昇さんの悪戯だとわかったこともあった。
新聞の外に草双子の借り読みもしていました。清水さんの声で、オイ升さん、御上使ってなんぞな、なんて言ったのが、今も耳についています。
磯子刀自はなお語り続けて、子規や清水の無精さを左の如く言っているが、その無精さ、無頓着さは清水の方が一枚上であった。清水は大学予備門時代に脚気を患い、夏休中その療養のために函根の某温泉に転宿したが、帰るに当たって何処か途中に懐中を遺失したので、帰途車にも馬にも乗る能はず、東京までトボトボと歩き通して遂に戻ったは戻ったが、そのため病気が悪化し、これより後三ヶ月ばかりして衝心のために突然斃れてしまった。その斃れるまで医者にも診せず、薬も服用せず、平気で毎日通学していたため、友人等もツイ注意を怠っていたと後に子規が悔やんで語っていた。磯子刀自の談というは次の通りである。
大の男が二人も居たって、宅のことは横のものを縦にもしない、と言って、主人が二人に、門の前の掃除と、手水鉢《ちょうずばち》の水の入れ替へを毎朝するように命じた。一人が箒を持って、そこらを掃いている中、一人は片手に塵取《ちりとり》をさげ、片手を懐手してポカンと待っている。貴様らのすることは、どうしてそう間が抜けているのか、と主人に叱られたりしたこともあった。
次には「翌十七年夏牛込に転じ」と記されている。これは同区東五軒町三十五番地をいったもので、藤野家の転居と共に子規も清水もここに移った次第である。六月七日付竹村鍛氏宛の端書に「小生表記之場所へ転所致候此段御報知申上候」と子規は言っている。何日にはとは書いていないが、同じく五月二十二日付竹村氏宛の端書は仲猿楽町藤野内よりとなっているから、、五月の下旬より六月の上旬に至るその十四五日間に行われたものと言い得るが、多分六月に入ってか転宅されたのであろう。その位地は今日の市電東五軒町停留所の近くであったと覚えている。磯子刀自は当時のその宅について次の如く語っている。
次は牛込の東五軒町の角の家でした。ここも四百坪もある大きな構えであったが、建坪はそう広くもなかったので、升さんは玄関の二畳に机を構えていた。しばらくしてから下宿をするようになったのです。
二畳しかない狭いところへ、いろいろ本を散らかして、足の踏み場もない、あれではお客さんが通れない、と言ってよく主人の小言をくっていました。
子規は玄関の二畳に居たとして、さて清水や古白は何処に居たのであろうか。子規一人居てさえ足の踏み場も無いと云うに、マサカ三人の男がこの二畳に混居していたとは思えない。予はこの家に一二回子規をたずねたに過ぎぬから、記憶が甚だ薄い。この時にも子規は食い意地を張って一混雑惹き起こしている。左は磯子刀自の思いでである。
私たちが蚊帳を買いに往くと言ったら、お留守番におすしのお土産をとの注文であったが、生憎おすしが間に合わず、餅菓子を買って来た。升さんはそれをたらふく食べた上、外にもお客さんがあって、晩餐に鰻丼をとった。升さんもも潔もお相伴をしたのだったが、お客さんの食べ残しまできれいに平らげてしまった。サアその晩吐瀉下痢の大騒ぎで、また大食の祟りだなんて笑って居られませんでしたが、実は餅菓子、鰻丼の外に、留守番をしている中、庭の青梅をこっそり食べたんだそうです。
語りおくれていたが、子規は須田学舎を退舎し、また久松邸内の書生小屋を引き払いて神田仲猿楽町の藤野漸氏方へ寄食せし際、駿河台の共立学校へ入学した。同校は英数学を主として漢学も教えていた。大学予備門の受験を志す者の準備教育を目的とするものと専ら称せられていた。予も当時しばらく同校に居たが、英学に高橋是清、志賀矧川、数学に隈本有尚といったような後年高名になった諸先生のあったことを覚えている。子規はこの八月同級生数輩と共に大学予備門の入学試験を受けた。未だ学力足らず到底合格の見込みはなかりしも、場慣れのためにと思って受験せしに過ぎざるに、意外にも合格したと本人は言っている。この満悦の情は「墨汁一滴」にも「筆まかせ」の半生の喜悲にも露骨に記されている。
次は「秋再び神田に来り」とある。神田区猿楽町五番地板垣善五郎方に下宿したのである。下宿の味を知りしは彼としてはこれが初である。夏六月に牛込に移居し、秋九月にこの下宿に這入ったのであるから、その東五軒町に往った期間は僅かに数月に過ぎなかったのである。「半生の喜悲」に子規は次の如く記している。
余は生まれてよりうれしきことにあい、思わずにこにことえみて平気でいられざりしこと三度あり。第一は在京の叔父のもとより余に東京に来れという手紙来りし時、第二は常盤会の給費生になりし時、第三は豫備門へ入学せし時なり。第一は数月前より遊思勃としてやまず、機会あらば夜ぬけなどせんと思いし時なればなり。第二は出京已来(いらい)食客にはいりこまんと方々の知らぬ人の処へいやながら行きしこと多く、それがため安心して学問出来ざりしその時にこの許しを得し故なり。第三はとても力足らぬ故入学は出来ずと思いし故なり。
従来子規の出京に反対していたる叔父加藤拓川から遂に上れとの手紙を得て、取敢えず出京したるその喜びを第一に、出京はなし得たるも家庭の都合上、今後学資を如何にして得んかとの不安を抱いて、或は久松家の書生小屋に自炊の辛酸を嘗め、或は親戚の家に寄食して気苦しき生活をなし、少しも落着いたる勉学の時間を有し得ざりしに当り、常盤会の給費生たるを許されてその不安を免れ得たる喜びを第二として、大学予備門に入学を志してその準備校たる共立学校に入学せしも日未だ浅く殊に英語の力足らずして到底合格の望無きに拘わらず、同級生等のすすめもありて場慣れのために予備門の試験を受けしに、意外にも意外倖い合格して驚喜したるを第三に数えつつこの「半生の喜悲」は草せられたものであるが、その第二の喜びたるや旧藩主久松家に育英事業の一つとして新たに設けられし常盤会給費生に選抜されしものにて、同家にては明治十六年六月以来旧藩内士族の優秀子弟にして学資乏しきため進んで勉学なし得ざる者に学資を給与せんとの議起こり、その準備中なりしが、、十七年の春に至りて愈々実施となり、藤野漸氏の推挙にて子規も清水則遠も選ばれて第一回の給費生中に加わりしは同年三月にて子規が予備門入学に先立つ六ヶ月前であった。給資は一ヶ月七円で書籍代は必要に応じて別に実費を給せらるる定めであったが、当時の下宿料は一円前後であり、学校の月謝も一円内外であったから、七円の給資は必ずしも貧弱というべきではなかった。大学に進んでは月十円となった。
この事実のうちに注目すべきことは、久松家に於いて貧困なる子弟に学資を給与せんとの議の起こりしは明治十六年六月以来にして、子規が叔父拓川の手紙を得て遽(すみや)かに出京せしもまた同六月の上旬であったという事である。拓川遺稿の日記中に「一日作答姪常規書」とあり、六月一日に子規宛の手紙を書いたのであるが、その内容はもとより知るに由なく、たとえこれを知り得たりとて子規等に久松家の内事など漏らすような手紙を書くとは想われぬが、この時拓川の胸裏を敢えて忖度(そんたく)してこの二事実の間に多少の関係があるように予は感じさせらるるのである。子規がそれを知っていたか否やは別として、拓川は久松家のこの新規計画を基礎として子規を遽かに東京に呼び寄せたものではなかったかと想うのである。何は兎も角この三拍子揃った幸運を祝福しつつ子規は寄食者の生活を脱し、天下晴れて一人前の学生生活を開始したのであった。
神田猿楽町五番地の板垣と称する下宿は近所に水原という内科の医院があって、その少し南方駿河台の方へ折れ曲がった横町に南向きに建てられし二階家で、当時ではかなり大きな下宿屋であった。水原医院は今の水原病院の先代であるかどうかは知らぬが、場所は同一である。清水則遠が脚気衝心でこの板垣で斃れた時に診断書を書いて貰ったのも水原医院であった。「新年二十九度」に「明治十八年は猿楽町の片隅に下宿屋の雑煮を喰いぬ」と子規は書いているが、これは板垣の時を言ったのである。
次に「十八年夏帰省し、再び出京して麹町区にあること二三日」と記されている。さて、この麹町区の場合が甚だ判りにくいのである。これに関して予の記憶は漠然として纏まらぬのである。子規の友人なる西原五州氏の説には、九段坂の北に中坂というがあって、その坂の中程に当時郷友二三名の居たある下宿屋があった。子規のいう麹町云々は想うにそこであったろう、慥(たし)かとは言えぬがおぼろにそんな記憶があるとの事であるが、予はこれに未だ同意し得ない。藤野磯子刀自の説には、子規の同郷で陸軍大尉の宇和川匡義という人が当時麹町番町に住んでいた。子規はある時、宇和川で牛肉の御馳走になって来た。軍人はサッパリしているなどと言ったのを覚えている。何のために宇和川をたずねしか、その用件も聞いたようだが忘れてしまった。子規の言う麹町にそれが関係ありや否やは知らぬが、この外に何等思い出し得ることがないとのことであるが、これまた本問題を解決するに足らぬと信ずる。
ただ漠然としてたよりなき予の記憶を語ってみることにする。明治十八年の夏休帰省から板垣に子規が帰ってきたと聞いて、ある朝予は訪問した。如何なる話の後であったか覚えぬが、二人で麹町に秋山真之氏の宅- その兄の陸軍騎兵中尉秋山好古氏の宅 - をたずねたが、その町名は今覚えていない。秋山の近所に何とか教会と称する基督教の会堂があったことと、同教の牧師として名の知られていた小崎弘道という人の住宅があったことは記憶に存している。ある人の説に好古氏は麹町区の平河町にも下二番町にも住居せしことありとのことなれど、我々が訪問せし十八年夏の場合は果たして何町でありしかということは判らぬ。格子戸を引きあげてすぐ靴脱ぎ、三畳の玄関の間、その奥が六畳の客室、客間の右に四畳半かの茶の間という間取なりしが、開け放った夏季のこと故、玄関に立って家のうち全部が見透かされていた。雇い婆さんらしいのが出て来て何か言っていたが、子規はすぐ客室に通った。予もついて上った。真之氏も主人の好古氏も折から不在なのであった。兎角するうちに正午になり、雇婆さんのすすむるままに午飯の馳走になって、我々は神田に帰ってきた。秋山訪問に就いてこれだけのことを覚えているのだが、考えてみると訳のわからぬことになる。よれゆえ予は漠然たる記憶だというのである。主人等の不在に拘らず容赦なく奥に上がり込みしは何故であろう。主人の命なきに雇婆さんの料簡で午飯を饗し、また我々はこれを受けて平然たり得しは何のためであろう。この点になると皆目わからぬことになる。当時はわかっていたから問題にせなかったのであろうが、記憶がぼけた今日では幾何考えても判らぬ。ただしこの点がわかると自然子規のいう麹町に在ること二三日云々の解決がつくのではないかというような気もするのである。
子規と秋山は大学予備門で同級でありしのみならず、同郷の小学校時代からの親友である。この夏両人ながら郷里に帰り、折々出会ったことであろう。何かの話の順から今度東京に帰ったら秋山の宅に同宿し、倶《とも》ども勉学しようではないかと云うような事になって、相携えて再び出京し、子規はその約束通り秋山の宅に入ったが、どうも不便なことが多くてそのまま居つづくことが出来ず、秋山の諒解を求めて元の下宿板垣方へ引移ったのではなかろうか。その二三日のなじみで雇婆さんとも懇意になりしため、主人が不在にも拘わらず奥にも通し午飯も饗したのではなかったろうか。これは固より憶測である。想像によりて作り上げしものではあるが、こういう風に解釈せば予の漠然たる記憶は一応整備して洵に好都合なのである。子規の文献も疑問なくして済むわけだが、軽々しく測断を下して糊塗すべきでないから、麹町の二三日は不明のまま未解決のままに措くとする。
陋屋 : 狭くみすぼらしい家
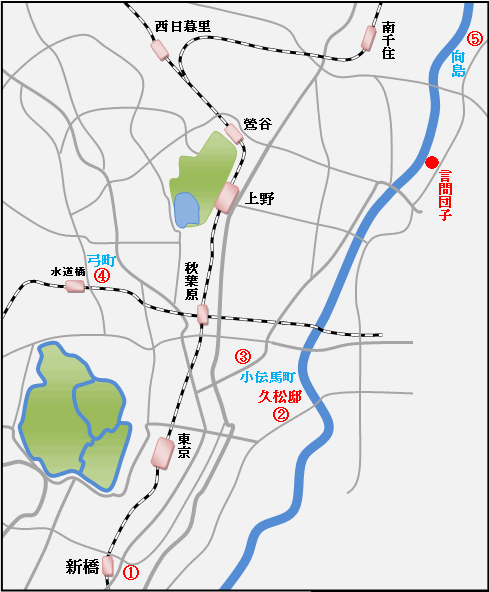
東京到着後の子規の行動 (駅や幹線道路は現在の位置)
①新橋停車場→②久松邸→③小伝馬町→④柳原の下宿→⑤加藤の下宿